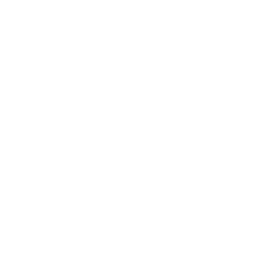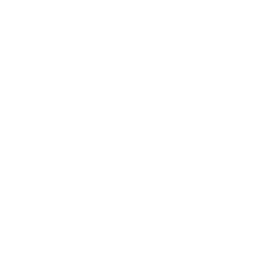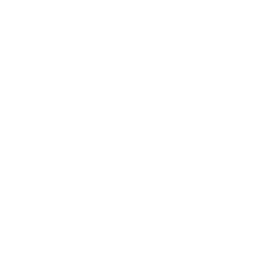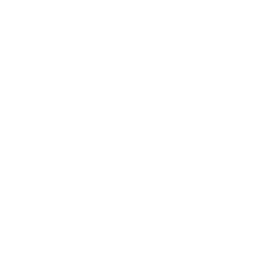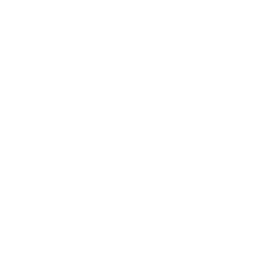だしの苦みを消すには?苦くなる理由と美味しいだしを取る方法を紹介

だしは日本料理の要であり、さまざまな料理に豊かな旨味を与えてくれる存在です。そのためだしに苦みが出てしまうと、せっかくの料理の風味を全て台無しにしてしまいます。本記事ではだしが苦くなる主な原因と、苦くならないだしの取り方について解説します。今回紹介する内容を参考にして、スッキリとした旨味を楽しめるだしの取り方をマスターしましょう。
この記事を読むための時間:3分
だしが苦くなる原因とは?
だしが苦くなる原因はさまざまですが、煮込み時間や、材料の扱い方に問題がある場合がほとんどです。今回は、だしが苦くなる主な原因として以下3つの内容について詳しく解説します。
- 煮込み過ぎによる苦み
- 材料の分量間違いによる苦み
- アク取り不足による苦み
煮込み過ぎによる苦み
だしを取る際に最も注意すべき点が火加減と煮込み時間です。材料の種類によって煮込む時間は異なりますが、一般的にだしを火にかけ過ぎると、えぐみや苦みが出やすくなります。特に昆布の場合、苦みだけでなくぬめり成分まで溶け出てしまうため、高温で煮込むとスッキリとしただしの旨味が楽しめません。だしを取る際は、材料ごとに適した火加減と煮込み時間をあらかじめ確認しておきましょう。
材料の分量間違いによる苦み
だしの材料と水の比率が適切でないと、苦みが強く出てしまう場合があります。美味しいだしを取るには適量の材料を使用しなければなりません。例えば昆布だしの場合は水1リットルに対して10~15グラム程度の昆布を使用するのが一般的です。かつお節の場合は水1リットルに対して20~30グラム程度が適量です。
適量以上の量を使用すると、旨味よりも苦みが勝ってしまいます。また煮干しだしは、煮干しの頭や内臓を取り除かずに使用するとさらに苦みが強くなるので注意してください。
アク取りの不足による苦み
だしを取る際に発生するアクをしっかりとすくい取らないと、苦みや雑味が強くなります。特に煮干しや椎茸、かつお節を使用しただしはアクが出やすいため、スッキリとした味わいを楽しむには、丁寧に取り除かなければなりません。
だしの苦みは消せるのか?
残念ながら、一度苦くなっただしから苦みを完全に取り除くのは難しいです。しかし、汁物を作る際に少量ずつ加えたり水で薄めて他の料理に使用したりすることで、多少の苦みを和らげることはできます。ただし本来のだしの風味を最大限に味わうことはできません。やはり、だしを取る過程で苦みを発生させないことが最も重要です。
苦くならないだしの取り方
美味しく、苦みのないだしを取るためには、以下3つのポイントを押さえなければなりません。
- 適切な温度、時間を守る
- 分量を守る
- アクを取る
だし作りで特に重要なのが適切な温度と時間を守ることです。昆布だしは60度前後のお湯で30分~1時間、かつおだしは沸騰したお湯に30秒~1分など、素材に応じた適切な抽出時間を守りましょう。もし適切な温度と時間を守ることに自信がなければ、水の中に素材を入れておくだけの水出しがおすすめです。
また、煮干しや干し椎茸を使用する場合は、材料の分量を守るだけでなく、頭と内臓を取り除いたり表面の粉を軽く払ったりするなどの下処理を丁寧に行うことも重要です。さらに煮出している間に浮いてくるアクは、だしの風味を損なう原因になるためこまめに取り除いてください。このようなポイントを押さえることで、苦みのない美味しいだしを取ることができます。
苦みのないスッキリとしただしで料理を楽しもう
本記事ではだしが苦くなる主な原因と、苦くならないだしの取り方について解説しました。だしが苦くなる原因を理解し、正しい方法でだしを取ることで、素材本来の味を引き立てる料理を作ることができます。下処理や水の温度、煮込み時間など今回紹介したポイントを押さえながら、美味しいだし作りに挑戦してみてください。