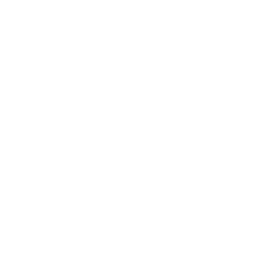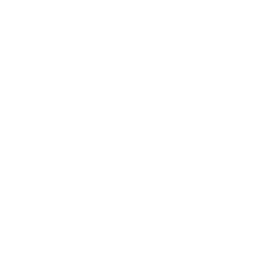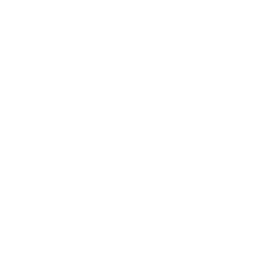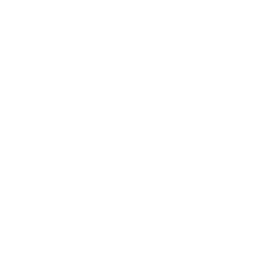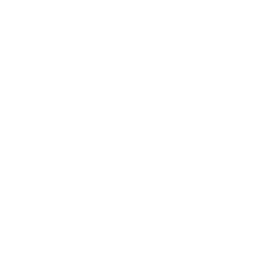炭水化物量が多い食べ物は?摂取量の目安や食べ方のポイントを解説

ダイエットの際、炭水化物を減らしがちだという方も多いのではないでしょうか。しかし、炭水化物は、私たちの毎日の生活に欠かせないエネルギー源であり、減らしすぎると非常に危険です。今回は、炭水化物を多く含む食べ物について解説します。摂取量の目安や食べる際のポイントもお伝えするので、ぜひ最後までご覧ください。
この記事を読むための時間:3分
炭水化物とは
炭水化物とは、身体のエネルギー源となる糖質と腸内環境を整える食物繊維で構成される、人体に欠かせない栄養素です。バランスよく炭水化物を摂取することで、健康的な体を維持することができます。
炭水化物を摂取するメリット
炭水化物は、身体のエネルギー源であることはよく知られていますが、それに加えて、脳の働きをサポートし、集中力や持続力を高める効果も認められています。また、全粒穀物や芋類など一部の炭水化物は食物繊維を豊富に含んでおり、腸内環境を整える効果が期待できます。
炭水化物を豊富に含む食べ物
炭水化物を豊富に含む食べ物は、以下の通りです。
- 穀物(ご飯、パン、麺)
- 砂糖
- フルーツ
- いも・でんぷん類
穀物(ご飯、パン、麺)
ご飯やパン、麺類などの穀物類は、炭水化物の代表的な供給源です。これらは主食として食べることが多いため、一日の炭水化物摂取量の大部分を占めます。100gあたりの炭水化物量を比較すると、白米が37.1g、食パンが46.4g、うどんが21.6g、中華麺が29.2gほどとなっており、パンや麺類よりもご飯の炭水化物量の方が多いです。
砂糖
砂糖は単純炭水化物の一緒に分類されており、スイーツやジュースなどに含まれています。無意識のうちに摂取しすぎている可能性があるため、糖質制限中はできるだけ避けてください。
フルーツ
フルーツには、自然な糖分が豊富に含まれているため、エネルギー源として非常に優れています。特に、バナナは炭水化物量が多く、手軽にエネルギーを補給したいときにおすすめです。またドライフルーツは、水分が抜けていることで栄養が凝縮されているため、一個あたりの炭水化物量が多めです。おやつとして食べる場合には、過剰摂取に注意しましょう。
いも・でんぷん類
さつまいもやじゃがいも、かぼちゃなどには、炭水化物が豊富に含まれています。100gあたりの炭水化物量を比較してみると、じゃがいもが17.3g、里芋が13.1g、長芋が13.9gであるのに対し、さつまいもは31.9gと非常に多い炭水化物を含んでいるのが特徴です。
カロリーと炭水化物の摂取量の目安
ここでは、カロリーと炭水化物の1日の摂取量の目安を、男女別に紹介します。エネルギー消費量や体格によっても個人差があるため、体重の変化などを考慮しながら摂取量を調整してみてください。
男性
1日の活動量が普通程度の場合、年齢別のカロリー必要量は以下の通りです。
18歳〜29歳…2,650kcal
30〜49歳…2,700kcal
50〜64歳…2,600kcal
ここから1日に摂取すべき炭水化物量を計算すると、18歳〜64歳においては、330〜430g程度が目安になります。
女性
1日の活動量が普通程度の場合、年齢別のカロリー必要量は以下の通りです。
18歳〜29歳…2,000kcal
30〜49歳…2,050kcal
50〜64歳…1,950kcal
1日に摂取すべき炭水化物量として、18歳〜64歳の成人女性は250〜320g程度を目安にしましょう。
炭水化物を食べる際のポイント
炭水化物を食べる際には、適切な量を守ると同時に食べ方のコツを押さえることも大切です。
- 穀類やいも類を中心に
- よく噛んで食べる
- 先に野菜や海藻を食べる
穀類やいも類を中心に
一口に炭水化物といっても、さまざまな種類のものがありますが、お菓子やジュースからではなく穀類やいも類を中心に摂取しましょう。穀類やいも類には、食物繊維やビタミンなどの体に必要な栄養素が豊富に含まれているため、健康的なダイエットに役立ちます。
よく噛んで食べる
炭水化物は、よく噛んで食べることにより消化が促進されるため、満腹感を感じやすくなります。また早食いは、血糖値急上昇を引き起こし太りやすくなるため注意が必要です。
先に野菜や海藻を食べる
炭水化物を多く含む食べ物を食べる前に、食物繊維を含む海藻やきのこ、野菜などを先に食べる習慣を身に付けましょう。食物繊維を豊富に含む食べ物を先に食べることで、糖質の吸収が穏やかになり、血糖値の急上昇を防ぐことができます。また、食事内容の栄養バランスも良くなるため、健康的な食事の習慣を作るためにも最適な方法です。
炭水化物を食べて健康的な身体を作ろう!
炭水化物はさまざまな食べ物に含まれていますが、主食となる穀物やいも類から摂取することが大切です。健康的に炭水化物を摂取したい方は、本記事の内容をぜひ参考にしていただき、ヘルシーな食習慣を身に付けましょう。